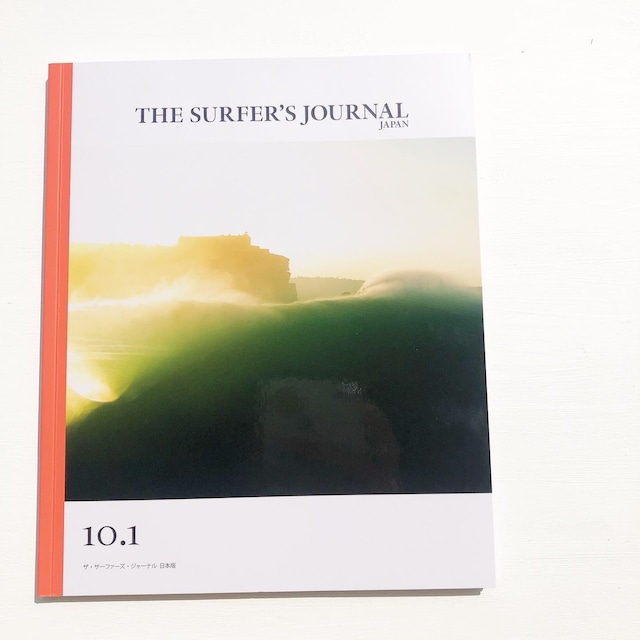世界中の読者に20年間の長きにわたって愛されもっとも信頼されるサーフィン専門誌 The Surfer's Journal 誌の日本語版。 米 The Surfer's Journal誌は、サーフィン関連の出版界で長年活躍し、世界中からリスペクトされるス ティーブとデビーのペズマン夫妻によって1991年に出版されました。
『ザ・サーファーズ・ジャーナル日本語版』は、本誌TSJのフランスにつづくあたらしい外国語バージョンです。文化的にもビジネス的にも世界的な影響を持つまでに成長したサーフィン。このすばらしく深淵なスポーツを、“SURF CULTURE"というあたらしい切り口からふかく掘りさげ、20年というながきにわたって世界中のサーフィンを愛する人々に紹介してきたTSJ。その編集コンセプトとスタンスを正統に継承し、本物の“SURF CULTURE"を日本のサーフィン愛好家たちにむけて発信しています。
世界でもよりすぐりのトップ・フォトグラファーたちによってとらえられた、サーフィンのうつくしく迫力に みちた瞬間の数々。新旧さまざまなライターたちによってつづられる、ふかい洞察に満ちた本質的でバラエ ティに富んだストーリー。 その価値ある内容は、魅力的なデザインによってレイアウトされ、最高の技術によるマットストック紙 への印刷で極限のうつくしさを主張しながら、最高の品質で編集されてきました。
そのクオリティはまさに アートの域にまで達していると、世界中で高い評価を受けつづけています。 米 The Surfer's Journal誌は、まさにプレミアム的な価値をもった出版物として、雑誌と書籍の中間に 位置づけられれてきた希有な存在なのです。 そんな米 The Surfer's Journal誌と日本の外国人むけアウトドア専門誌を発行するOutdoor Japan Media社が提携し、本国オリジナル版の完全日本語版化をめざした『ザ・サーファーズ・ ジャーナル 日本語版』は、デザインもレイアウトも印刷もすべてオリジナル版のクオリティを踏襲し、 オリジナル版の内容を日本語でおつたえすることを目的に発行される本格派です。サーファーという生き方 を深く考察し、この日本を拠点にサーファーとしての生き方を追求するみなさんはもちろんのこと、あたらし い生き方をもとめるすべての人々にむけて、人生のあらたなたのしみ方を提案するライフスタイル・マガジンです。
今回のコンテンツは、
<フィーチャーストーリー>
今号の日本版のオリジナルコンテンツは、1978年に故村瀬勝宏(以下エへ/1955-2007)とカメラマンの芝田満之がメキシコへ旅した道中記だ。1970年代後半、日本でも「知らない土地の知らない波に乗る」というディープなサーフトリップがはじまっていた。このサーフィン・カルチャーともいえるワイルドなサーフトリップはアメリカからはじまっていた。その醍醐味を1971年にメキシコなど中南米を旅したケビン・ニュートンは語っていた。「リスクと恩恵がつきまとった初期のサーフトリップは、カネより幸運に頼るしかなかった。正確な気象予報もサーフリゾートもない時代だ。でも、未知の波を求めて道なき道を行くそのフィーリングは、プライスレスのすばらしさだった。この時代のサーファーたちは噂だけを頼りにメキシコやヨーロッパ、そしてインドネシアへと旅立っていったんだから。後年、その無謀な行動は、その愚かさそっちのけで、栄光のサバイバル・ストーリーとして受け継がれていった」。エへと芝田もまた困難なメキシコの旅を通して、カルチャーショックにも触れ、バスの中ではウェットスーツを着たり、ローカルたちに石を投げられたり、サメの海に連れていかれるなどのさまざまなハプニングに満ちた体験をして、まわりのサーファーたちのヒーローになったのだが、それは、まさにその時代のサーファーという種族の文化そのものであったといえよう。
Tequila Sunrise, Tequila Sunset
「エへの旅立ち」
1978年、ふたりの日本人がメキシコのとある浜辺にたどり着いた。カリフォルニアのエンシニータスを出て1週間が経っていた。日本から直線距離でおよそ12,000km、そこはあの伝説ともなったペタカルコだった。
文:森下茂男
1978年10月、サーフィンカメラマンという職業を選んだばかりのサーフ・フリーク、芝田満之は、伊勢在住のサーフィン仲間で飲み友達の村瀬勝宏(以下、エへ)を誘って、カリフォルニアへと向かった。この旅に出る前、芝田にはある計画があった。「アメリカの『サーフィン』誌に「カモン、ルーキー」みたいなコーナーがあって、アーロン・チャングが撮影したブライアン・バークレーのすごい写真が載っていたんだ。キャプションにはメキシコって書いてあったけど、そこは当時注目のサープポイント、プエルト・エスコンディドだった。メキシコにもこんな波があるんだって、そのとき初めて知ったんだ。ぼくはそれまでああいう波が立つ場所はパイプラインしか知らなかったし、ジェリー・ロペスしか知らない時代に、アーロン・チャングがどでかいチューブに入っているブライアン・バークレーの写真を撮っているって、ぼくにとっては衝撃的なことだった。その写真がぼくの脳裏にすり込まれていて、そこへ行きたくてしょうがなかった」
つづいてのストーリーは、アート・ブルーワーみずから、お気に入りの写真からさらにふるいにかけた珠玉の写真の数々を掲載した「OFFERINGS(捧げ物)」だ。アート自身のキャプションと、当時、米『サーファー』誌でフォト・ラングラー(彼の補佐官)としてアートに仕えた新人編集員だったスティーブ・バリオッテイの文章で綴るフォトエッセイに仕上げている。
OFFERINGS
「捧げ物」
アート・ブルーワーの一期一会。
文:スティーブ・バリオッテイ
写真:アート・ブルーワー
あれは1992年だった。私たちはオークランドから1300海里の洋上にあるSSルーライン号の船尾にいて、ジョイントを吸っていた。不意に私はアート・ブルーワーを知ることがどんなに尊いものかという気持ちになった。もちろんアート・ブルーワーのことはすでに知っている。私が初めて米『サーファー』誌を手にした1975年の1冊にはすでにそのフォトクレジットがあった。ときどき掲載される彼の風景写真もスパイスが効き、雑誌の構成に有効な役割を果たしていた。
CLARE IN HIS BLOOD
「クレアの誓い」
トム・ロウ:ブリティッシュの島々が生んだワールドクラスのビッグウェーバー。
文:ダニエル・クローク
大西洋の端っこにコンパクトに凝縮したタマネギみたいな低気圧が回転し、そのビッグデーがはじまるまでの1週間は、どこもグッドウェーブに恵まれた。世界中でホットラインがうるさく鳴り響いていた。シェーン・ドリアンまでが飛行機に乗ってやってきていた。波を予測するとそのスケールとエネルギーは飛び抜けていて、まるで別の領域に足を踏み入れたかのようだった。そこは頂上から見るかぎりはビッグウェーブ・ポイントではなかった。緑の円形競技場というのがふさわしい。ここはトム・ロウが経験を積んだ場所。素人目に見ても、ここの波にはふたつの異なったテイクオフ・スポットがあるのがわかる。きみを北ヨーロッパの広い洞窟に投げ入れるアウトサイドのロール、そしてインサイドのレッジ(棚)はクレイジーなやつらが巨大なスラブ(厚板波)に挑戦する場所だ。
The Sikerei of the Islands
「島々のシケレイたち」
メンタワイ諸島を旅するひとりのサーファーが、シャーマンに出会い、彫り師に出会い、そして文化の衝突を目の当たりにした。
文、写真:マッティー・ハノン
替刃の針がぼくの胸に打ち込まれる。アマン・レポンはメンタワイのシャーマンで彫り師。素手で針をひたすら打ちつける。汚い爪だ。タンタンタンタンタン。針のついた木の棒を別の木の棒で叩く音が響き、激痛が胸を刺す。おなじリズムで永遠に彫りつづけてかれこれ10時間。意識がもうろうとし、半ば夢の中にいるような気分だった。彼の手が、ぼくの肌を引っ張るように広げる。ロングハウスの玄関に吊された頭蓋骨の奥から、幼い子供たちの笑い声が聞こえる。大量の虫が支配するこの鬱蒼としたジャングル。どす黒い雲が辺りを暗くし、雷が光ると雷鳴が轟いた。過酷な試練は、遂にぼくを追い詰めようとしていたのか、あるいはメンタワイの強烈な熱波にやられていたのだろう。空一面に広がる真っ黒な雲がぼくの身体を吸い上げる。熱帯の空の下、ぼくは戦っていた。やがて風が吹き、雨が降りはじめる。すると木陰のカエルが唄いだす。さらに1時間後、吹きやまぬその風は、ライフルズにも届いていることだろう。風が長周期スウェルとなり、1週間の旅を経てやってくる。ぼくはそこへ向かうボートの様子を思い浮かべた。きっと船内のサーファーたちは興奮度マックスにちがいない。このジャングルのロングハウスからは、ずいぶん遠い別の世界の出来事に感じる。
GOOD TROUBLE
「グッドトラブル」
デイブ・ラストビッチの果てしなき探求。
文:スティーブ・バリロッティ
写真:トッド・グレイザー
ラストビッチがずぶ濡れで屋根付きのベランダに戻ってくると、わたしたちは中断されていた会話を再開した。彼の足元は裸足で、上半身も裸、身にまとっているのは庭仕事用のショーツ一丁である。会話の内容は、メタガスコ社の資源探査に反対する地元民が推し進めた草の根運動についてだ。2014年、バイロンベイからおよそ40マイル南西の街リズモアで推し進められた炭層ガスの開発事業に対し、先住民アボリジニの人権活動家、農家、環境活動家、田舎暮らしの退職者、アーティストとダンサーと音楽家、くわえて変人のサーファー数人が珍しく一致団結したその抵抗運動は「ベントリー封鎖」として知られている。「サーファーを巻き込むことに成功すると、本格的なムーブメントに発展したって実感が湧いてくる。反対運動が盛りあがるにつれて、そんなジョークも飛び交うようになったんだ」ラストビッチは当時をふり返る。
Electric Blue Maybes
「エレクトリックブルーの波」
オアフ島の西海岸の報酬とリスク。
文:ボー・フレミスター
写真:レーザーウルフ&ジェレミア・クレイン
人が車に貼っている手がかりによって、オアフ島の西海岸にやってきことを気づかされる。ファリントン・ハイウェイを進むにつれ、ワイルドで手つかずの風景が広がっていく。乾いて灼けたリーワードコーストの大地、道端の質素な酒屋、バンパーステッカーのメッセージにも、変化を感じ取ることができる。ナナクリの手前で目にするステッカーは、「今日、あなたのケイキ(子供)を抱きしめた?」、「ポイは持った?」、「ドリー・パートン(カントリー歌手)のチケットのために働きます」なんて、いたって無害なものがほとんどだ。けれど、発電所を通り過ぎてワイアナエにむかうあたりから、「優等生はおれの犬が喰っちまったぜ」とか、「Watchufaka!(やんのか、この野郎! )」とか、「ノーハワイアン、ノーアロハ」(これは事実だと思うけれど)なんて感じに、急に物騒なメッセージが増えてくるのだ。
Portfolio: SA RIPS
ポートフォリオ:サ・リップス
「ポインタービルの西」
ホワイトシャークの望みはヘイデン・リチャーズとスイムアウトすること。
文:シーン・ドハーティー
ぼくたちはエリストンの郊外にあるブラックスの崖の上にいて、笑いで気を紛らしていた。東からやってくる旅のサーファーにとってブラックスは不気味な場所だ。本当は、ここはブラックフェラ(黒い連中)という地名。1849年にウォータールー湾で起こった大虐殺を皮肉って呼ばれるようになった。多くのアボリジニたちが白人の入植者たちによって崖から突き落とされたのだ。写真を撮れば波とサメと幽霊が写るような霊的にはヘビーな場所。今日の波はたった4フィートだが、三日月型をしたむき出しのリーフの上でそれはバレリングし、砕け散ると深い海に消えた。